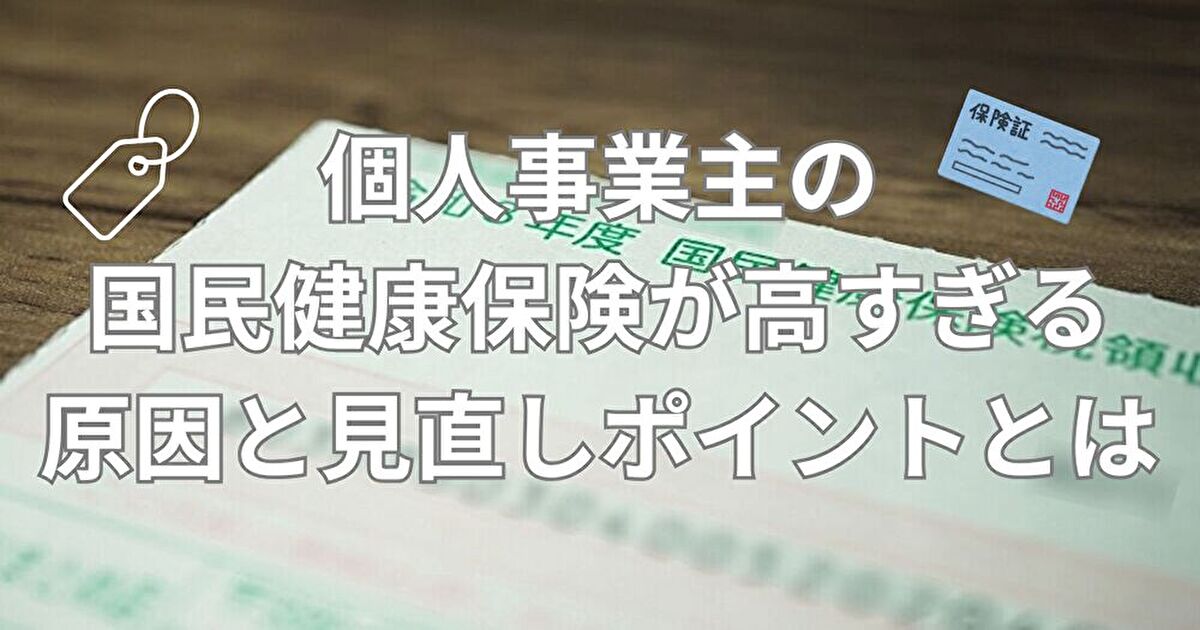個人事業主として働く中で、多くの人が負担に感じるのが国民健康保険の保険料ではないでしょうか。収入によって変動するため、個人事業主の国民健康保険はいくらから支払うのかと気になる人も多いはずです。特に、支払額が高すぎると感じる場合、国民健康保険 払わない方法や国民健康保険 安くする方法を知りたくなるでしょう。
本記事では、「個人事業主の国民健康保険の仕組み」や、「個人事業主 国民健康保険 免除」の条件、さらには「社会保険と国民健康保険ではどちらが得なのか」について詳しく解説します。また、「国民健康保険が高いのはなぜ」なのか、その理由と対策についても触れていきます。

国民健康保険の負担を少しでも軽くしたいと考えている人は、ぜひ最後まで読んでくださいね
個人事業主の国民健康保険が高すぎる?原因と対策
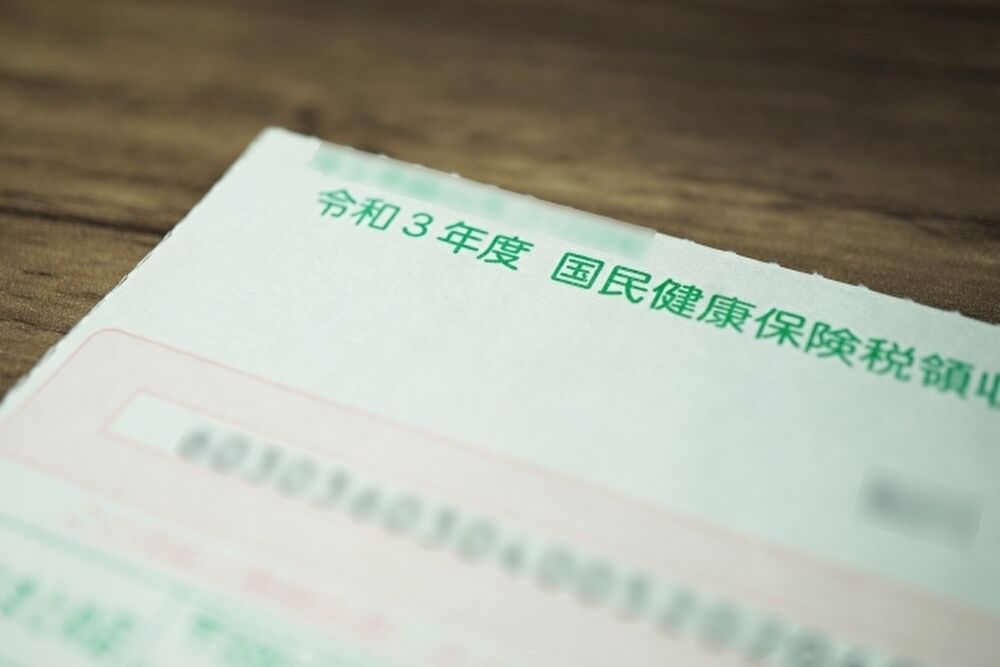
- 個人事業主の国民健康保険はなぜ高いのか?
- 個人事業主の国民健康保険はいくらから?
- 国民健康保険の最高額はいくら?
- 個人事業主の健康保険料をシミュレーションしてみよう
- 社会保険と国民健康保険ではどちらが得?
- 国民健康保険を安くする方法とは?
個人事業主の国民健康保険はなぜ高いのか?
個人事業主の国民健康保険料が高く感じられるのには、いくつかの理由があります。その最も大きな要因は、会社員とは異なり、保険料の負担をすべて自分でしなければならない点です。会社員の場合、健康保険料の半分は勤務先の企業が負担してくれますが、個人事業主はその恩恵を受けられません。
また、国民健康保険の保険料は、前年の所得を基準に計算されるため、事業が好調で前年に高い収入を得ていた場合は、翌年の保険料が大幅に増えることがあります。これに対し、会社員が加入する健康保険は、毎月の給与に応じて保険料が決まるため、収入の増減に即した負担となりやすい仕組みになっています。
さらに、国民健康保険には扶養という概念がない点も、高額になりやすい理由の一つです。会社員が加入する社会保険の場合、一定の条件を満たせば配偶者や子どもを扶養に入れることができ、家族の分の保険料を追加で負担する必要はありません。
しかし、国民健康保険にはそのような制度がなく、家族の人数分だけ保険料が発生するため、世帯全体の負担が大きくなります。加えて、自治体ごとに保険料の計算方法や負担割合が異なるため、住んでいる地域によっても負担額に差が出ます。都市部や財政が厳しい自治体では、保険料が高めに設定されることがあり、同じ収入でも地域によって支払額が変わることも少なくありません。
このような理由から、個人事業主の国民健康保険料は高くなりがちです。しかし、保険料の軽減措置や節税対策をうまく活用することで、負担を減らす方法もあります。
個人事業主の国民健康保険はいくらから?
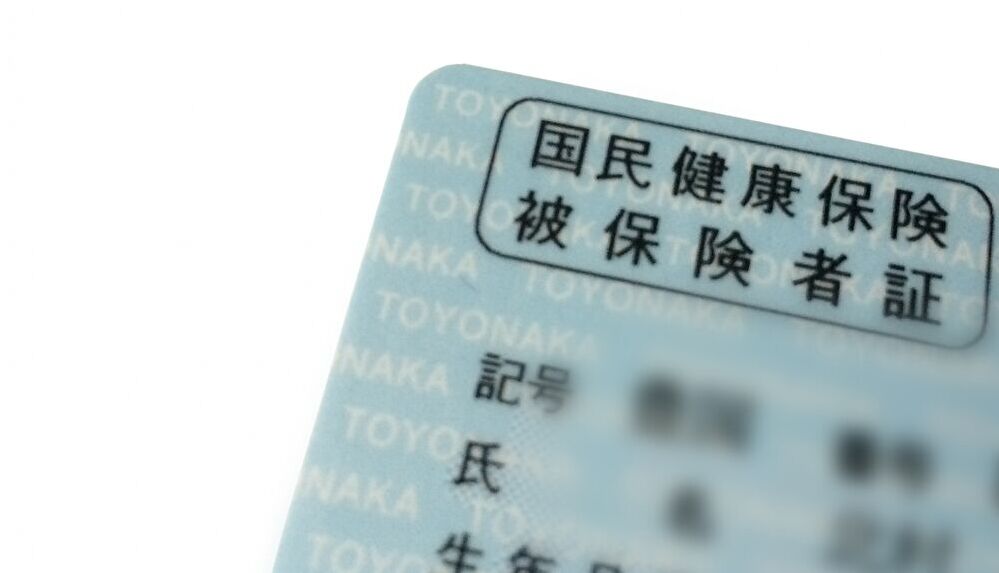
国民健康保険の保険料は、住んでいる自治体によって異なりますが、収入がゼロであっても一定額は発生します。具体的な金額は自治体ごとに設定されているため、正確な数値を知るには市区町村のウェブサイトで確認するか、役所に問い合わせる必要があります。
一般的には、国民健康保険の保険料は「所得割」「均等割」「平等割」「資産割」の4つの要素で計算されます。ただし、資産割を採用していない自治体もあります。
所得割は前年の所得を基準にした計算式で決まり、所得が増えればその分だけ保険料も上がる仕組みです。一方で、均等割と平等割は、収入に関係なく一律で発生する部分で、均等割は加入者1人ごとにかかる費用、平等割は世帯単位でかかる費用となっています。
では、具体的に「いくらから」支払うことになるのでしょうか。
例えば、東京都23区のケースを見てみると、仮に前年の所得がゼロであっても、均等割と平等割の合計として年間数万円の負担が発生することが多いです。収入がない場合、減免制度が適用されるケースもありますが、全額免除とはならず、最低限の保険料を支払う必要があります。
また、開業したばかりで前年の収入がない場合でも、自治体によっては所得割の部分がゼロになり、最低額のみを支払うことになります。しかし、翌年以降に収入が増えると、その分の保険料が上がるため注意が必要です。
国民健康保険料は、単純に「いくらから」と一律で決まるものではなく、住んでいる自治体や収入によって異なるため、事前に計算シミュレーションをしておくことが重要です。
国民健康保険の最高額はいくら?
国民健康保険の保険料には上限が設けられており、どれだけ高収入であっても、それ以上の金額は課されません。最高額は自治体によって若干の違いがありますが、2024年度の基準では、年間の上限額は約100万円前後に設定されているケースが多く見られます。
具体的には、国民健康保険料の上限額は、主に「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分(40歳以上の場合)」の3つに分かれています。医療分の上限は65万円、後期高齢者支援金分の上限は22万円、介護保険分の上限は17万円(40歳以上の場合)となっており、合計すると年間100万円以上になることもあります。
たとえば、前年の所得が数千万円ある高所得の個人事業主であっても、これらの上限額を超える保険料を支払う必要はありません。そのため、収入が増えれば増えるほど保険料の負担率は低くなり、実質的な負担感が軽減される仕組みになっています。
ただし、これはあくまで「1人分の上限額」であり、世帯単位で考えるとさらに保険料がかかる場合があります。国民健康保険には扶養制度がないため、家族の人数が増えるほど、一人ひとりの均等割や平等割が加算され、結果として総額が高額になるケースもあります。
また、自治体によっては、特定の減免措置が設けられていることがあり、所得が一定以下の場合は保険料の負担が軽減される場合があります。たとえば、前年の収入が大幅に減少した場合や、災害・病気などの特別な事情がある場合には、減額や免除を申請できることもあります。
国民健康保険の最高額は、個人の収入や家族構成によって異なりますが、一般的には年間100万円前後が目安となります。保険料の上限を把握した上で、無駄な負担を減らすための対策を考えることが重要です。
個人事業主の健康保険料をシミュレーションしてみよう
個人事業主の健康保険料は、所得や居住地によって大きく異なります。そのため、事前にシミュレーションを行い、おおよその負担額を把握しておくことが重要です。国民健康保険の保険料は「所得割」「均等割」「平等割」「資産割」の4つの要素で計算されますが、具体的な計算方法は自治体ごとに異なります。
たとえば、前年の所得が400万円の個人事業主が東京都23区に住んでいる場合、国民健康保険料はおよそ40万~50万円程度になります。これに対し、同じ所得の会社員であれば、協会けんぽや健康保険組合に加入することになり、保険料の半額を会社が負担してくれるため、実際の支払額は25万円前後に抑えられるケースが一般的です。
国民健康保険料の具体的な金額を計算するには、市区町村の公式サイトにあるシミュレーションツールを活用するのが便利です。これにより、所得金額や家族構成を入力するだけで、おおよその保険料を把握することができます。
また、今後の収入予測を基に、どの程度の保険料負担が発生するのかを試算し、節税対策や社会保険への切り替えを検討することも重要です。
なお、国民健康保険には扶養制度がないため、配偶者や子どもがいる場合は、家族一人ひとりに保険料がかかります。そのため、扶養制度のある社会保険と比較すると、家族が多いほど保険料の負担が重くなりやすい点に注意が必要です。
事前にシミュレーションを行い、自身の状況に合った最適な健康保険の選択肢を考えることで、不必要な負担を減らすことができます。

社会保険と国民健康保険ではどちらが得?
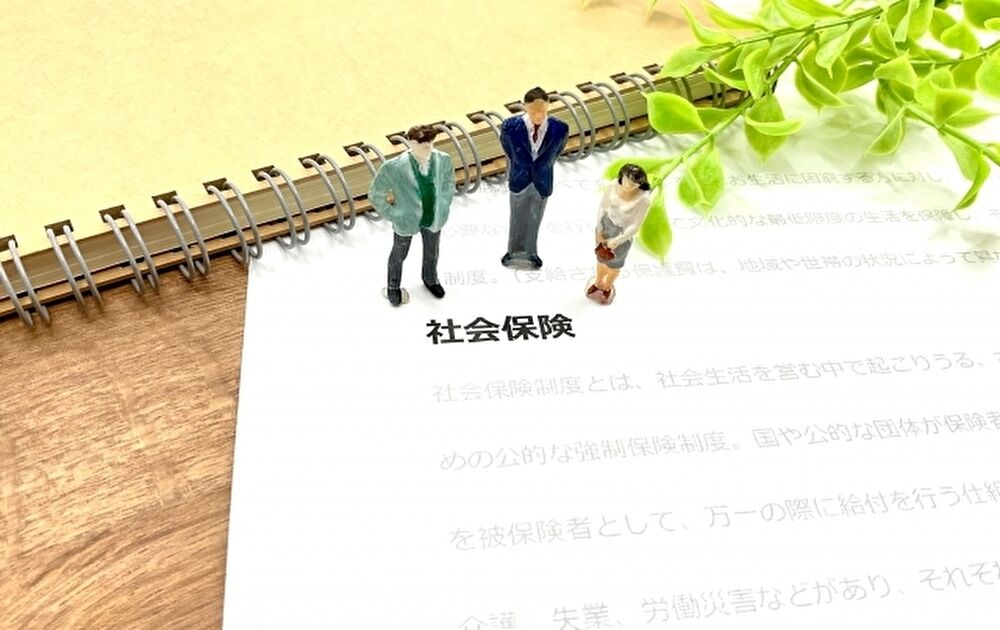
個人事業主が加入できる健康保険には、大きく分けて「国民健康保険」と「社会保険(健康保険組合や協会けんぽ)」の2種類があります。どちらが得かを考えるには、保険料の負担額だけでなく、扶養の有無や保障内容を総合的に比較することが大切です。
まず、保険料の面では、社会保険のほうが有利なケースが多くなります。社会保険では、加入者が支払う保険料の半分を会社(法人)が負担するため、実際に支払う金額は国民健康保険よりも少なくなることが多いです。
たとえば、年間50万円の保険料が発生する場合、社会保険では会社が25万円を負担してくれるため、個人の負担額は25万円で済みます。一方で、国民健康保険は全額自己負担となるため、収入が高くなるほど負担が重くなります。
また、社会保険には「扶養制度」がある点も大きなメリットです。国民健康保険では、配偶者や子どもを扶養に入れることができず、家族の人数分だけ保険料が加算されます。しかし、社会保険では、一定の条件を満たせば配偶者や子どもを扶養に入れることができ、その分の追加負担が発生しません。
ただし、社会保険に加入するには、法人を設立して役員報酬を受け取るか、一定の条件を満たす「個人事業主向けの健康保険組合」に加入する必要があります。そのため、すべての個人事業主が自由に選択できるわけではなく、事業の状況によっては国民健康保険のほうが適している場合もあります。
どちらが得かを判断する際には、収入の規模や家族構成、法人化の可能性などを総合的に考えることが重要です。将来的に事業が拡大し、安定した収入が見込める場合は、社会保険への切り替えを検討するのも良い選択肢の一つです。
国民健康保険を安くする方法とは?
個人事業主にとって、国民健康保険料の負担は大きな悩みの一つです。しかし、いくつかの方法を活用することで、保険料を安く抑えることが可能です。
まず、最も一般的な方法は「所得を抑える」ことです。国民健康保険の保険料は、前年の所得に応じて計算されるため、経費を最大限活用して課税所得を下げることで、翌年の保険料を軽減できます。たとえば、小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの制度を活用し、節税対策を行うことで、保険料の負担を抑えることができます。
次に、自治体の「減免制度」を活用する方法もあります。自治体によっては、収入が一定額以下の場合や、特定の条件を満たす場合に、保険料の減額や免除が受けられる制度があります。例えば、前年に比べて収入が大幅に減少した場合や、災害・病気などの理由で支払いが困難になった場合には、役所に相談することで減免措置が適用される可能性があります。
さらに、社会保険への切り替えを検討することも一つの選択肢です。個人事業主でも、条件を満たせば「個人事業主向けの健康保険組合」に加入することができる場合があります。また、法人化することで、社会保険に加入し、保険料の負担を軽減することも可能です。法人化にはデメリットもありますが、保険料の削減だけでなく、年金の充実や経費計上の幅が広がるなどのメリットもあります。
また、引っ越しによって保険料を抑える方法もあります。国民健康保険の保険料は自治体ごとに異なるため、同じ所得でも居住地を変えることで負担額を下げられる場合があります。ただし、住民票の移動には手続きが必要であり、生活環境の変化も伴うため、慎重に検討することが重要です。
このように、国民健康保険を安くする方法はいくつかありますが、自身の状況に応じて最適な手段を選ぶことが大切です。保険料を適正な範囲に抑えながら、将来の健康リスクにも備えるバランスの取れた対策を考えていきましょう。
個人事業主の国民健康保険が高すぎると感じたら試すべきこと
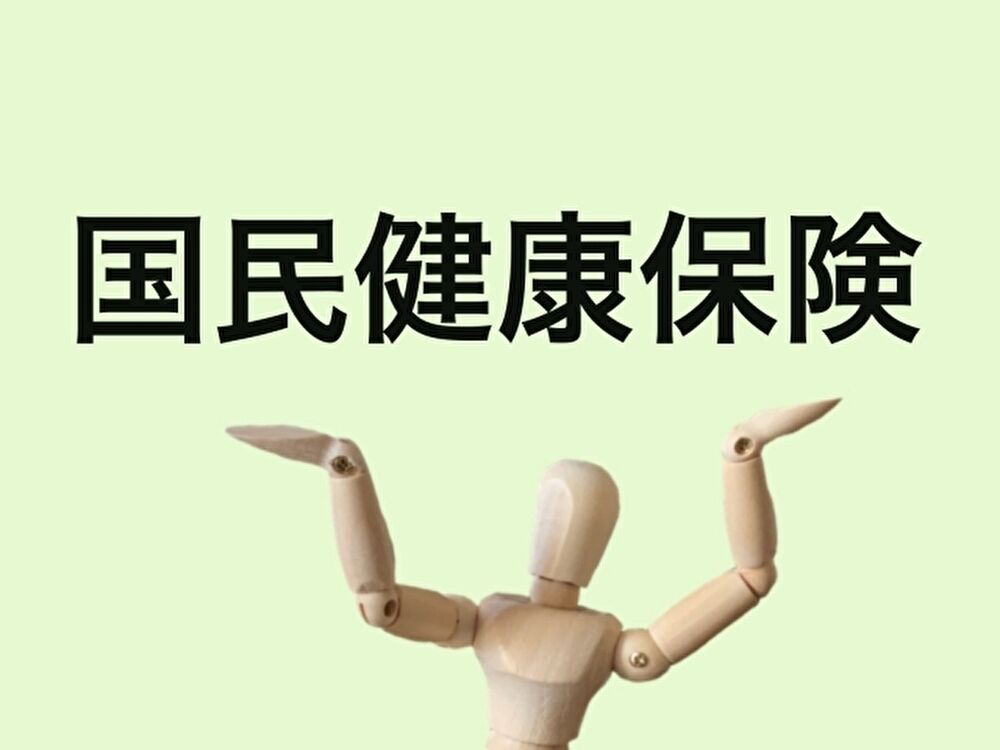
- 国民健康保険を払わない方法はある?
- 個人事業主が利用できる健康保険組合一覧
- 国民健康保険の免除を受ける条件とは?
- ふるさと納税で国民健康保険を節税できる?
- その他の節税対策で保険料を抑える方法
- 個人事業主の国民健康保険は高すぎる?負担が重い実態とは
国民健康保険を払わない方法はある?
国民健康保険は、日本に住むすべての人が加入しなければならない公的医療保険制度の一つです。そのため、基本的に「支払わなくてもよい方法」は存在しません。ただし、特定の条件を満たすことで、保険料の免除や減額を受けたり、他の健康保険制度に切り替えたりすることで負担を軽減することは可能です。
まず、支払いが困難な場合は「減免制度」を活用できます。自治体ごとに異なりますが、前年と比べて収入が著しく減少した場合や、災害・病気・失業などの理由で経済的に厳しい状況にある場合、申請によって保険料の減額や免除が認められることがあります。この制度を利用するには、役所に申請書を提出し、必要な証明書類を添える必要があります。
また、別の健康保険制度に切り替える方法もあります。たとえば、個人事業主でも法人化すれば社会保険に加入でき、国民健康保険から抜けることができます。法人の役員として健康保険組合や協会けんぽに加入することで、扶養家族の分の保険料が発生せず、結果として負担を減らせる可能性があります。
配偶者が会社員や公務員で社会保険に加入している場合、その扶養に入ることで国民健康保険を脱退することも可能です。ただし、年間収入が130万円(60歳以上や障害者の場合は180万円)未満であること、被扶養者としての認定基準を満たすことなど、条件があるため注意が必要です。
一方で、国民健康保険料を意図的に支払わないままでいると、最終的に財産の差し押さえなどの厳しい措置が取られる可能性があります。滞納が続くと、未納期間に応じて督促状が届き、延滞金が発生するだけでなく、健康保険証の使用が制限されることもあります。そのため、支払いが厳しい場合は、役所に相談し、減免制度の利用や分割納付の交渉を行うことが重要です。
個人事業主が利用できる健康保険組合一覧
個人事業主は原則として国民健康保険に加入しますが、一定の条件を満たせば、国民健康保険以外の健康保険組合に加入することも可能です。主に「特定の業界団体が運営する健康保険組合」や「フリーランス向けの健康保険制度」などがあり、国民健康保険よりも保険料が抑えられたり、手厚い保障を受けられたりするメリットがあります。
代表的な健康保険組合として、以下のようなものがあります。
・対象者:作家、イラストレーター、写真家、デザイナーなどのクリエイター
・特徴:国民健康保険よりも保険料が安く、全国どこでも加入可能
・対象者:芸能関係者(俳優、声優、演奏家など)
・特徴:東京都に事務所を持つ芸能関係者が加入できる
・対象者:建設業に従事する個人事業主やその従業員
・特徴:建設業界に特化した健康保険で、保険料が比較的安価
・対象者:全国の土木・建築業に携わる個人事業主
・特徴:全国対応で、建築関係のフリーランスが加入しやすい
・対象者:開業医や個人で活動する医師
・特徴:医療関係者専用の健康保険組合で、手厚い保障を受けられる
・対象者:法人化したIT関連企業の経営者や従業員
・特徴:個人事業主は加入できないが、法人化すれば加入可能。保険料が安く、保養施設や補助金などの福利厚生が充実している
個人事業主が健康保険組合に加入するためには、各組合の加入条件を満たす必要があります。業界団体への所属が求められるケースもあるため、事前に公式サイトで詳細を確認することが大切です。
また、業界団体の国民健康保険組合に加入できない場合でも、法人化することで「協会けんぽ」や「健康保険組合」に加入することも検討できます。これにより、国民健康保険よりも保険料が抑えられるケースもあるため、事業の状況に応じて最適な選択肢を考えましょう。
国民健康保険の免除を受ける条件とは?
国民健康保険料の支払いが厳しい場合、一部または全額の免除を受けることが可能です。ただし、免除が適用されるには、一定の条件を満たし、自治体へ申請を行う必要があります。
一般的に、国民健康保険の免除が適用されるケースは以下のようなものがあります。
事業の業績悪化や失業などにより前年よりも収入が大幅に減少した場合、自治体に申請することで保険料の減額や免除が認められることがあります。具体的な基準は自治体ごとに異なりますが、例えば所得が一定額以下である場合、軽減措置が適用されることがあります。
生活保護を受給している人は、原則として国民健康保険料の支払いが免除されます。この場合、医療費は生活保護制度の医療扶助でまかなわれるため、健康保険料を支払う必要はありません。
地震や台風などの災害、または病気やケガにより長期間働けなくなった場合、保険料の減免措置を受けられる可能性があります。申請には、罹災証明書や診断書などの証明書類が必要になることが多いため、自治体の窓口で確認しましょう。
所得が一定額以下の障害者、未成年者、寡婦(夫)については、国民健康保険料の軽減措置が適用されることがあります。具体的な軽減額や適用条件は自治体によって異なります。
免除や減免を受けるには、役所の窓口で申請手続きを行う必要があります。自治体ごとに適用条件や手続き方法が異なるため、まずは居住地の役所に相談し、自分の状況に合った支援を受けられるか確認することが大切です。
ふるさと納税で国民健康保険を節税できる?
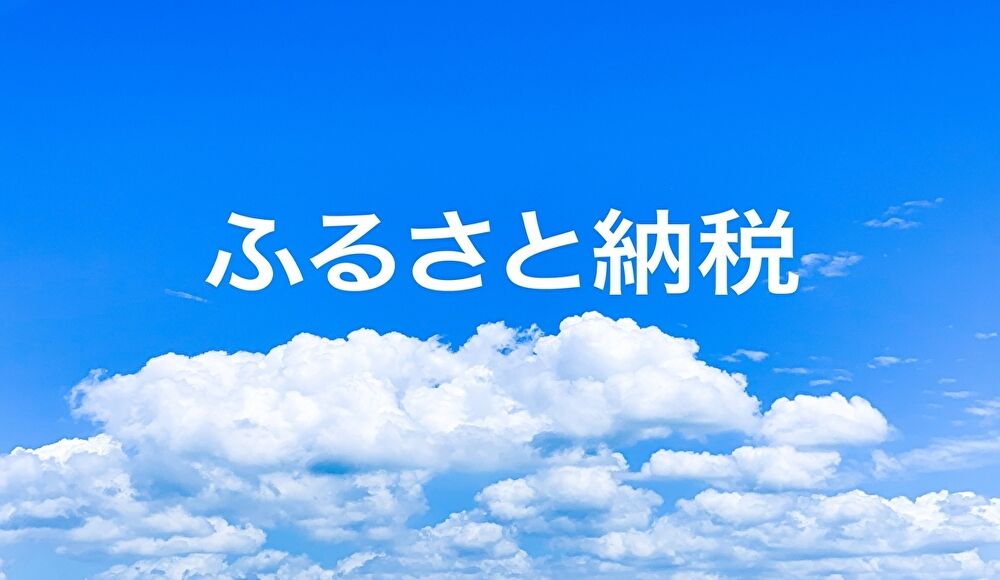
ふるさと納税は、自己負担2,000円で全国の自治体に寄付できる制度で、寄付額の一定割合が所得税や住民税から控除される仕組みです。これにより税負担が軽減されるため、結果的に国民健康保険料の節税にもつながる可能性があります。
まず、国民健康保険料の計算方法を理解しておくことが重要です。国民健康保険の保険料は、所得に応じて決まる「所得割」が大きな割合を占めます。所得割の計算では、総所得金額から基礎控除や各種所得控除を差し引いた「課税所得」が基準となります。そのため、課税所得を減らすことができれば、国民健康保険料の負担も軽くなります。
ふるさと納税は、寄付金控除の対象となるため、控除後の課税所得を引き下げる効果があります。具体的には、ふるさと納税で寄付を行うと、その寄付額(自己負担の2,000円を除く)が所得税と住民税の控除対象となり、課税所得が減少します。課税所得が下がることで、国民健康保険の所得割部分も低くなるため、結果的に保険料の節税につながるのです。
ただし、ふるさと納税を活用した場合でも、住民税の控除額が大きすぎると控除限度額を超えてしまい、十分な節税効果が得られないことがあります。また、所得控除の影響を受けるのは「所得割」のみであり、均等割や平等割といった固定部分の保険料には影響しません。そのため、ふるさと納税を行うことで国民健康保険料がゼロになるわけではなく、あくまでも一定の節税効果が見込める程度と考えておくとよいでしょう。
ふるさと納税の節税効果を最大化するには、自分の所得に応じた適切な寄付額を把握することが重要です。寄付の上限額は年収や家族構成によって異なるため、ふるさと納税のシミュレーションを活用して、自分にとって最適な寄付額を確認することをおすすめします。
また、ふるさと納税は自治体への寄付であり、返礼品が受け取れるというメリットもあります。食品や日用品などを選ぶことで、実質的な生活費の節約にもつながるため、賢く活用することで二重のメリットを得られるでしょう。
その他の節税対策で保険料を抑える方法
国民健康保険料は所得に応じて決まるため、課税所得を抑えることで保険料を軽減することができます。そのためには、ふるさと納税以外にもさまざまな節税対策を活用することが重要です。ここでは、個人事業主が実践できる代表的な節税方法を紹介します。
小規模企業共済は、個人事業主が将来の廃業や引退に備えて積み立てる共済制度で、掛金は全額所得控除の対象になります。たとえば、月額5万円(年間60万円)を積み立てると、その分の所得が控除されるため、課税所得を減らすことができます。結果として、所得税・住民税の負担が軽くなるだけでなく、国民健康保険料の軽減にもつながります。
iDeCoは、自分で積み立てる年金制度で、掛金の全額が所得控除の対象になります。たとえば、年間27.6万円(個人事業主の上限額)を積み立てた場合、その分の所得が控除されるため、課税所得が減り、国民健康保険料も下がる可能性があります。ただし、iDeCoは60歳まで引き出せないというデメリットがあるため、長期的な視点での活用が必要です。
個人事業主の場合、事業に関連する支出は経費として計上でき、課税所得を圧縮することが可能です。たとえば、事業用のパソコンやソフトウェア、通信費、家賃(自宅兼事務所の場合は按分)などを適切に経費にすることで、所得を減らし、国民健康保険料の節税につなげることができます。ただし、事業と関係のない支出を経費として計上することは認められていないため、適正な範囲での申告が必要です。
青色申告を行うことで、最大65万円の所得控除を受けることができます。この控除を受けるには、複式簿記で帳簿をつけ、確定申告時に青色申告として提出する必要があります。青色申告特別控除を適用することで、課税所得を減らし、結果として国民健康保険料の負担を軽減できます。
家族が事業に従事している場合、「専従者給与」として給与を支払うことで、事業主の所得を抑えることが可能です。専従者給与を経費として計上すれば、結果的に課税所得が減少し、国民健康保険料の節税につながります。ただし、適正な金額である必要があり、税務署に事前届出が必要な点には注意が必要です。
これらの節税対策を組み合わせることで、所得税や住民税の負担を軽減し、国民健康保険料の負担も抑えることができます。ただし、制度ごとに条件や制限があるため、自分の事業状況や将来の計画に合わせて最適な方法を選択することが大切です。税理士や専門家に相談することで、より効果的な節税プランを立てることも検討するとよいでしょう。
個人事業主の国民健康保険は高すぎる?負担が重い実態とは
国民健康保険についてまとめます。
- 国民健康保険の保険料は所得に応じて決まる
- 事業の売上が増えると保険料も急増する
- 会社員の健康保険と比べて自己負担が大きい
- 退職して個人事業主になると保険料負担が増えるケースが多い
- 配偶者の扶養に入れないため、家族全員の保険料が発生する
- 住んでいる自治体によって保険料の差が大きい
- 40歳以上になると介護保険料も加算される
- 所得が低くても一定額の保険料負担がある
- 事業が赤字でも保険料の支払い義務がある
- 減免制度はあるが、条件が厳しく適用されにくい
- 保険料の支払いが厳しいと滞納リスクが高まる
- 滞納すると保険証が使えなくなる可能性がある
- 会社員のように事業主負担がないため全額自己負担
- 確定申告の控除額が少ないと保険料が増える
- 将来的な負担増加の可能性が指摘されている