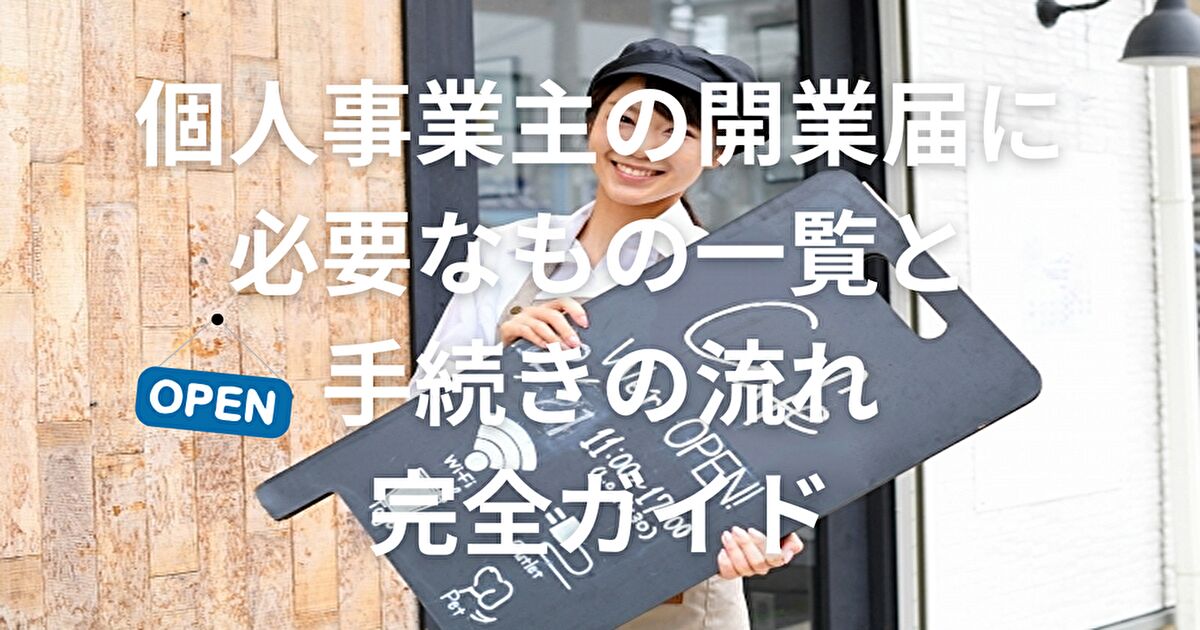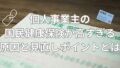個人事業主として事業を始める際に必要となるのが開業届です。開業届とは何か、その概要や提出の目的を理解し、正しく手続きを進めることが重要になります。
開業届を提出するには、必要な書類を揃え、事前に準備を整えておくことが求められます。では、具体的にどのような書類や情報が必要なのか、どこで開業届を入手し、どこに提出すればよいのかを詳しく見ていきましょう。
開業届の提出方法には、税務署へ直接提出する方法とe-Taxを利用する方法があります。正しい書き方や記入のポイントを押さえて、スムーズに手続きを進めることが大切です。また、開業届は売上が0円の状態でも提出すべきなのか、出さないとどうなるのかといった疑問についても解説します。
さらに、開業届を提出する最適なタイミングや、どのくらいの収入があれば提出すべきなのかといった点も押さえてます。開業届と併せて提出するとよい書類もあり、事前に知っておくことで後の手続きがスムーズになります。
本記事では、個人事業主が開業届を出す際に必要なものを詳しく解説し、手続きの流れや注意点をわかりやすく紹介します。

ぜひ参考にしてくださいね
- 個人事業主が開業届を提出する目的や、提出することで得られるメリット
- 開業届を出す際に必要な書類の種類や、事前に準備しておくべきもの
- 開業届の具体的な提出方法や、提出先となる税務署の確認方法
- 開業届を出すべき理由や、提出しない場合に発生するデメリット
個人事業主が開業届を出すために必要なもの
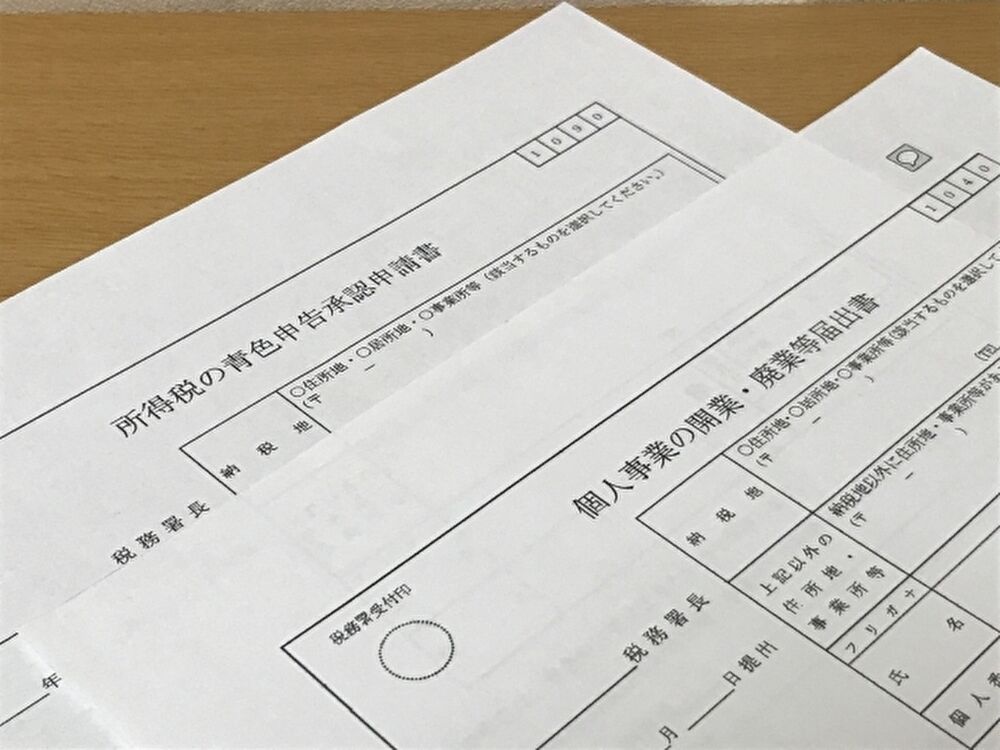
- 開業届とは?概要と提出の目的
- 開業届に必要な書類と準備するもの
- 個人事業主の開業届はどこに提出する?
- 開業届のダウンロード方法と入手場所
- 開業届の正しい書き方と記入のポイント
- e-Taxで開業届を提出する手順と書き方
開業届とは?概要と提出の目的
開業届とは、個人事業主が事業を開始したことを税務署に申告するための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、税務署に提出することで、国や自治体に対して事業の開始を公式に知らせる役割を果たします。
開業届を提出する目的は、大きく分けて二つあります。
一つ目は、税制上の優遇措置を受けるためです。開業届を提出することで、「青色申告承認申請書」も同時に提出できるようになり、これにより青色申告が可能になります。青色申告を利用すると、最大65万円の控除や、赤字を翌年以降に繰り越せる制度が適用されるため、節税効果が期待できます。
二つ目の目的は、社会的な信用を得るためです。開業届を提出することで、公的に事業を行っている証明となり、銀行での事業用口座の開設や、クレジットカードの作成、融資の申請がしやすくなります。また、取引先によっては、個人事業主としての正式な証明を求められることもあるため、スムーズな取引のためにも開業届の提出が役立ちます。
ただし、開業届を提出すると「個人事業主」として税務署に認識されるため、確定申告が必要になることを理解しておく必要があります。特に、所得が一定額を超えると、住民税や事業税の負担が発生することも考慮しなければなりません。そのため、事業の規模や収益見込みを考えたうえで、開業届の提出を検討するとよいでしょう。
開業届に必要な書類と準備するもの
開業届を提出する際には、いくつかの書類と準備すべきものがあります。まず、基本となるのが「個人事業の開業・廃業等届出書」です。この書類は税務署の窓口で直接もらうこともできますが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。手書きでも作成できますが、パソコンで記入して印刷することもできます。
次に、「青色申告承認申請書」も重要な書類の一つです。開業届と同時に提出することで、青色申告が利用できるようになり、最大65万円の控除や帳簿付けの簡便化といったメリットを受けることができます。ただし、開業後2ヶ月以内に提出しなければ翌年からの適用となるため、早めに準備することが大切です。
また、開業届を提出する際には、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要になる場合があります。特に、e-Taxを利用してオンラインで提出する場合は、マイナンバーカードと対応するICカードリーダーが必要になるため、事前に確認しておきましょう。
開業届を提出する前に、事業の概要を整理しておくことも重要です。具体的には、事業の名称や業種、事業を行う住所、屋号(任意)などを決めておくと、記入がスムーズに進みます。特に屋号は、今後の名刺や請求書、銀行口座の開設時にも関わるため、慎重に選ぶとよいでしょう。
さらに、事業を始めるにあたっては、必要な設備や資金の準備も欠かせません。例えば、フリーランスのライターであればパソコンやインターネット環境、デザイナーであればデザインソフトやタブレットなど、業種に応じた道具を揃える必要があります。
また、事業用の銀行口座を作成しておくと、経理処理がしやすくなり、確定申告の際にも役立ちます。
個人事業主の開業届はどこに提出する?

個人事業主の開業届は、原則として「事業を行う住所を管轄する税務署」に提出します。自宅で事業を営む場合は、自宅の住所を管轄する税務署、事務所や店舗を借りている場合は、その所在地を管轄する税務署が提出先となります。税務署の所在地は、国税庁のホームページで検索できるため、事前に確認しておきましょう。
開業届の提出方法には、大きく分けて3つの方法があります。
まず、一つ目は「税務署の窓口で直接提出する方法」です。税務署に足を運び、書類を提出すれば、その場で受理され、控えを受け取ることができます。控えは今後の手続きで必要になる場合があるため、紛失しないように保管しておくことが大切です。
二つ目は「郵送で提出する方法」です。遠方に住んでいる場合や、税務署に行く時間がない場合は、郵送での提出が可能です。この際、提出した証明として控えを受け取りたい場合は、返信用封筒(切手貼付・宛名記入済み)を同封すると、受理後に控えが返送されます。
三つ目は「e-Tax(電子申告)」を利用してオンラインで提出する方法です。e-Taxを利用すれば、税務署に行く手間が省け、24時間いつでも手続きが可能です。ただし、利用するには「マイナンバーカード」と「ICカードリーダー」が必要になります。
また、事前にe-Taxの利用者識別番号を取得する必要があるため、初めて利用する場合は準備に時間がかかることを理解しておきましょう。
いずれの方法でも、開業届を提出したからといって審査があるわけではなく、基本的には書類を提出すれば受理されます。ただし、記入ミスがあると修正が求められるため、提出前に内容をしっかりと確認することが大切です。
開業届のダウンロード方法と入手場所
開業届は、税務署の窓口でもらうこともできますが、インターネットからダウンロードして印刷することも可能です。国税庁の公式サイトでは、開業届(正式名称:「個人事業の開業・廃業等届出書」)のPDFが無料で提供されており、いつでも入手できます。
まず、国税庁のホームページにアクセスし、「税務手続き」や「申告・届出手続」のカテゴリーを選択します。そこから「個人事業主向けの届出・申請書一覧」を開くと、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」が見つかるため、該当するPDFをダウンロードしましょう。ファイルを開くと、記入欄が用意されており、手書きでもパソコン上での入力でも対応可能です。
また、開業届は最寄りの税務署の窓口でも無料で入手できます。窓口で職員に開業届が欲しいことを伝えれば、その場で用紙をもらうことができます。窓口では、開業届の記入方法についての簡単な説明を受けられる場合もあるため、記入に不安がある方は直接税務署に足を運ぶのも良い方法です。
さらに、近年では「確定申告ソフト」や「開業支援サービス」を提供する企業のウェブサイトでも、開業届のフォーマットが提供されていることがあります。これらのサイトでは、必要な情報を入力するだけで、自動的に開業届のPDFが作成される便利なツールも利用できるため、パソコンやスマートフォンでスムーズに作業を進めたい方に適しています。
開業届を入手した後は、事業の概要や事業開始日、屋号などを事前に整理し、記入作業をスムーズに進めることが重要です。
開業届の正しい書き方と記入のポイント
開業届の書き方は決して難しくありませんが、正しく記入することで後の手続きをスムーズに進めることができます。記入ミスがあると、税務署から訂正を求められる可能性があるため、各項目の意味を理解しながら慎重に書きましょう。
開業届には、主に以下の情報を記入します。
-
氏名・住所・生年月日
まず、事業主の基本情報を記入します。氏名は戸籍上の正式なものを記入し、住所も住民票の記載通りに正確に書きましょう。 -
屋号(任意)
屋号は事業の名称にあたるもので、法人でいう「会社名」に相当します。例えば、「○○デザインスタジオ」や「△△コンサルティング」といった形で自由に設定できます。ただし、後から変更も可能なため、慎重に決める必要はありません。 -
開業日
事業を開始した日付を記入します。開業届の提出期限は開業から1ヶ月以内とされていますが、厳密な証明は求められないため、実際の業務開始日を基準に考えましょう。 -
事業の概要
事業の内容を具体的に記入します。例えば、Webライターであれば「インターネット上の記事執筆業務」、デザイナーであれば「ロゴ・広告デザイン制作業」など、簡潔にまとめます。曖昧な表現を避け、税務署の職員が事業内容を理解しやすいように書くことがポイントです。 -
所得の種類
通常、個人事業主の所得は「事業所得」に該当します。ただし、不動産の賃貸業などを行っている場合は「不動産所得」となるため、事業の実態に合ったものを選択しましょう。 -
青色申告の適用希望の有無
節税のメリットを活かすためには、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出することをおすすめします。青色申告を選択すると、最大65万円の控除が受けられるため、税負担を軽減できます。
記入が終わったら、内容を見直し、誤字脱字や不備がないかを確認しましょう。また、提出する際には、控えを作成し、税務署の受付印をもらうことで、開業届の提出証明として保管することができます。
e-Taxで開業届を提出する手順と書き方
e-Taxを利用すれば、開業届をオンラインで提出できるため、税務署に足を運ぶ必要がなく、手続きの手間を大幅に削減できます。特に、マイナンバーカードを持っている方は、スムーズに電子申請が可能です。
1. e-Taxの利用環境を準備する
まず、e-Taxを利用するために必要なものを揃えます。以下の準備が必要です。
- マイナンバーカード
- ICカードリーダー(パソコンで提出する場合)
- e-Tax対応のソフトウェアまたは「e-TaxのWeb版」
また、スマートフォンからでも提出可能ですが、その場合はマイナポータルと連携する必要があります。
2. e-Taxのサイトにアクセスし、利用者識別番号を取得する
e-Taxを初めて利用する場合は、国税庁の「e-Taxホームページ」にアクセスし、利用者識別番号(16桁の番号)を取得する必要があります。これは、オンラインで税務手続きを行うための個別識別番号となります。
3. 開業届の電子申請を行う
利用者識別番号を取得したら、e-Taxの「Web版」または「確定申告書等作成コーナー」にログインし、「個人事業の開業・廃業等届出書」のフォームを開きます。画面の指示に従い、必要事項を入力しましょう。紙の開業届と同様に、氏名・住所・事業内容・開業日などを記入します。
4. 電子署名を行い、送信する
すべての項目を入力したら、電子署名を行い、開業届を送信します。電子署名にはマイナンバーカードが必要で、ICカードリーダーまたはスマートフォンのマイナポータルアプリを使用して認証を行います。送信が完了すると、受付完了の通知が表示され、手続きが完了します。
5. 受付完了の確認と控えの保存
送信後は、e-Taxのマイページで受付状況を確認できます。控えをPDFでダウンロードし、保存しておくと、後に開業届を提出した証明として利用できます。
e-Taxを活用すれば、自宅からでも簡単に開業届を提出できるため、時間を有効に使いたい方にはおすすめの方法です。
個人事業主の開業届を出すべき理由と注意点

- 開業届は売上0円でも提出するべき?
- 開業届を出さないとどうなる?デメリットを解説
- 開業届は何月に出すのがベスト?
- 開業届はいくら稼いだら提出すべき?
- 開業届と併せて提出しておくとよい書類
- 個人事業主の開業届に必要なものとは?まとめ
開業届は売上0円でも提出するべき?
開業届は、売上が0円の状態でも提出したほうが良いとされています。個人事業主として活動を始めた時点で、税務署へ開業の意思を伝えることが重要だからです。では、なぜ売上がなくても開業届を出したほうが良いのか、その理由を詳しく解説します。
まず、開業届を提出することで「青色申告」が可能になります。青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除を受けることができ、節税効果が高まります。ただし、青色申告をするためには「青色申告承認申請書」を開業届と同時に提出する必要があります。もし、開業届を出していないと、この青色申告ができなくなり、結果的に税負担が増える可能性があります。
また、開業届を出すことで、事業に関連する経費を適切に計上できるようになります。たとえば、パソコンやインターネット回線費用、事業用の交通費などが経費として認められやすくなります。売上が0円であっても、これらの経費を計上することで、赤字を翌年以降に繰り越すことができ、将来的な税金負担を軽減できます。
さらに、社会的な信用の面でもメリットがあります。開業届を提出すると、屋号で銀行口座を開設できる場合があり、ビジネス専用の口座を持つことで取引先や顧客に対する信用が向上します。また、事業用クレジットカードの発行や、各種ビジネス向けサービスの利用がしやすくなるため、個人事業を本格的に進めるうえで有利に働きます。
一方で、開業届を出すと「住民税の均等割」や「国民健康保険料の変動」といった影響があるため注意が必要です。例えば、住民税の均等割(自治体によって異なりますが、おおよそ5,000円〜7,000円程度)は事業の収益に関係なく課されるため、開業後に売上がなかなか伸びない場合でも一定の負担が発生します。
しかし、これらの点を踏まえても、将来的なメリットを考えれば、売上0円の段階で開業届を出しておく価値は十分にあると言えます。
開業届を出さないとどうなる?デメリットを解説
開業届を出さずに個人事業を始めた場合、すぐに罰則があるわけではありません。しかし、開業届を提出しないことによるデメリットはいくつか存在します。
まず、大きな影響を受けるのが「青色申告ができないこと」です。青色申告には最大65万円の控除があるため、開業届を出さずに白色申告をする場合、税金の負担が増えてしまいます。また、青色申告では赤字の繰り越しが最大3年間可能ですが、白色申告の場合はこの制度が利用できません。
つまり、初年度に経費が多くかかって赤字になった場合でも、翌年以降の利益と相殺できないため、結果的に節税の機会を逃してしまいます。
次に、開業届を出さないと「事業としての経費計上が認められにくい」点もデメリットの一つです。確定申告の際に、税務署に対して事業としての実態を説明する必要があり、開業届を提出していないと、事業経費として認められにくくなるケースがあります。
特に、自宅を仕事場としている場合の「家賃や光熱費の一部を経費にする」などの処理が難しくなることも考えられます。
また、社会的な信用にも影響を及ぼします。例えば、事業用の銀行口座を開設しようとした際に、開業届を求められる場合があります。さらに、個人事業主向けの融資制度や補助金・助成金を利用したい場合にも、開業届の提出が前提条件となっていることが多いため、事業の拡大を考えたときに不都合が生じる可能性があります。
開業届を提出しないこと自体に罰則はありませんが、こうしたデメリットを考慮すると、早めに提出しておいたほうが将来的なメリットが大きいと言えます。
開業届は何月に出すのがベスト?
開業届を提出するタイミングは、事業を開始した日から1ヶ月以内とされていますが、実際には「どのタイミングで出すか」によって税制上のメリットが変わることがあります。では、開業届を出すのに最適な時期について詳しく解説します。
まず、最もおすすめのタイミングは「年初(1月〜3月)」です。これは、青色申告を利用する場合、1年分の収支をしっかりと管理できるためです。特に、1月に開業届を提出すると、その年の1月1日から事業を開始したとみなされるため、経費の管理がしやすくなります。
また、年をまたいで事業を開始すると、途中から記帳を始めることになり、確定申告時に複雑な処理が必要になるため、できるだけ年初からスタートするのが理想的です。
一方で、「年末(10月〜12月)」に開業届を出す場合も、節税効果を考えるとメリットがあります。例えば、その年に大きな経費が発生する予定がある場合、年末に開業届を出しておくことで、その経費を当年分の事業経費として計上できます。
これにより、所得を圧縮し、税金の負担を軽減することができます。ただし、年末に開業すると、その年の確定申告期間が短くなるため、事務処理の負担が増える可能性があります。
また、「開業届を出すタイミングをあえて調整する」という考え方もあります。例えば、副業として事業を始める場合、本業の収入が安定している間は開業届を出さず、事業の売上が一定額に達した段階で提出するという方法もあります。
ただし、青色申告を適用するためには開業届を早めに提出する必要があるため、長期的な視点で判断することが重要です。
開業届の提出時期には明確な正解はありませんが、「事業開始の時期」「節税の観点」「事務処理の負担」などを総合的に考慮して、最適なタイミングを選ぶことが大切です。
開業届はいくら稼いだら提出すべき?
開業届は、特定の金額に達した時点で提出しなければならないという決まりはありません。しかし、一般的な目安として「継続的に事業所得が発生する状態」であれば、提出するのが望ましいとされています。では、どのような基準で判断すればよいのでしょうか?
まず、税務上の観点から考えると「事業所得」と「雑所得」の違いが重要です。たとえば、年間で数万円〜十数万円程度の収入があり、それが単発の副業や趣味の延長線上で得たものであれば、税務署に事業として認められにくく、開業届を出す必要はないと判断されることが多いです。
一方で、継続的に収入を得ている場合や、本業として活動する場合は、たとえ売上が少なくても開業届を提出したほうが良いでしょう。
次に、確定申告との関係を考えると「年間20万円以上の利益(所得)」が一つの目安になります。副業の場合、給与所得がある人は、年間の副業による所得(売上から経費を引いた額)が20万円を超えると確定申告が必要になります。このラインを超えるようであれば、開業届を提出し、青色申告のメリットを活かすことを検討すべきです。
また、開業届を提出することで、青色申告が可能になり、最大65万円の特別控除が受けられます。売上が少ないうちから青色申告を活用することで、節税効果を高めることができます。たとえば、売上がまだ少なくても、事業にかかった経費(パソコン代、通信費、備品代など)を適切に計上することで、所得を抑えることができます。
さらに、社会的な信用という観点でも、開業届を出すことで「事業を正式に開始している」ことを証明できます。たとえば、屋号付きの銀行口座を開設したい場合や、事業用のクレジットカードを作る際に、開業届の控えが必要になるケースがあります。
したがって、売上がまだ少なくても、今後本格的に事業を続けるつもりがあるなら、早めに開業届を提出するのが賢明です。一方で、副業として細々と収入を得るだけで、特に税制上のメリットを活かす必要がない場合は、売上や利益が一定の額に達してから検討するのも一つの方法です。
開業届と併せて提出しておくとよい書類

開業届を提出する際には、事業をスムーズに進めるために、いくつかの書類を同時に提出しておくことをおすすめします。これらの書類を事前に用意しておくことで、税制上のメリットを最大限に活かし、後々の手続きを簡略化できます。
まず、最も重要なのが「青色申告承認申請書」です。これは、青色申告を希望する場合に必要な書類で、開業届と同時に提出するのが一般的です。青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除が受けられるほか、赤字を3年間繰り越せるという大きなメリットがあります。青色申告をするには、事前に承認を受ける必要があり、事業開始から2ヶ月以内に提出しなければなりません。そのため、開業届と一緒に出しておくとスムーズです。
次に、「給与支払事務所等の開設届出書」も必要になる場合があります。これは、事業主が従業員を雇う場合に提出する書類で、たとえアルバイトや家族に給与を支払う場合でも、税務署に届け出る必要があります。青色申告を利用する場合、家族への給与を「専従者給与」として経費にできる制度があるため、家族を事業に関与させる場合は、この書類を出しておくと節税につながります。
また、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」も検討するとよいでしょう。これは、従業員や外注スタッフに支払う報酬の源泉徴収を毎月ではなく、半年に一度のまとめ払いにできる制度です。資金繰りの負担を軽減するためにも、対象となる事業主は申請を考えておくとよいでしょう。
さらに、自治体によっては「事業開始等申告書」が必要な場合があります。これは、個人事業を開始したことを市区町村に届け出るための書類で、住民税の計算に関係してきます。提出義務があるかどうかは自治体によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
このほか、場合によっては「開業資金に関する書類」も用意しておくとよいでしょう。特に、開業資金を金融機関からの融資で調達しようと考えている場合、事業計画書や資金繰り表の提出を求められることがあります。日本政策金融公庫などの公的融資を利用する際には、これらの書類が審査に影響するため、事前に準備しておくとスムーズです。
これらの書類は、開業届と同時に提出することで、後々の手続きが簡単になり、事業を円滑に進めるうえで大きなメリットがあります。特に、税務上の優遇措置を受けるためには、適切なタイミングで必要な書類を提出することが重要です。開業届を出す際には、これらの書類も忘れずに準備しておきましょう。