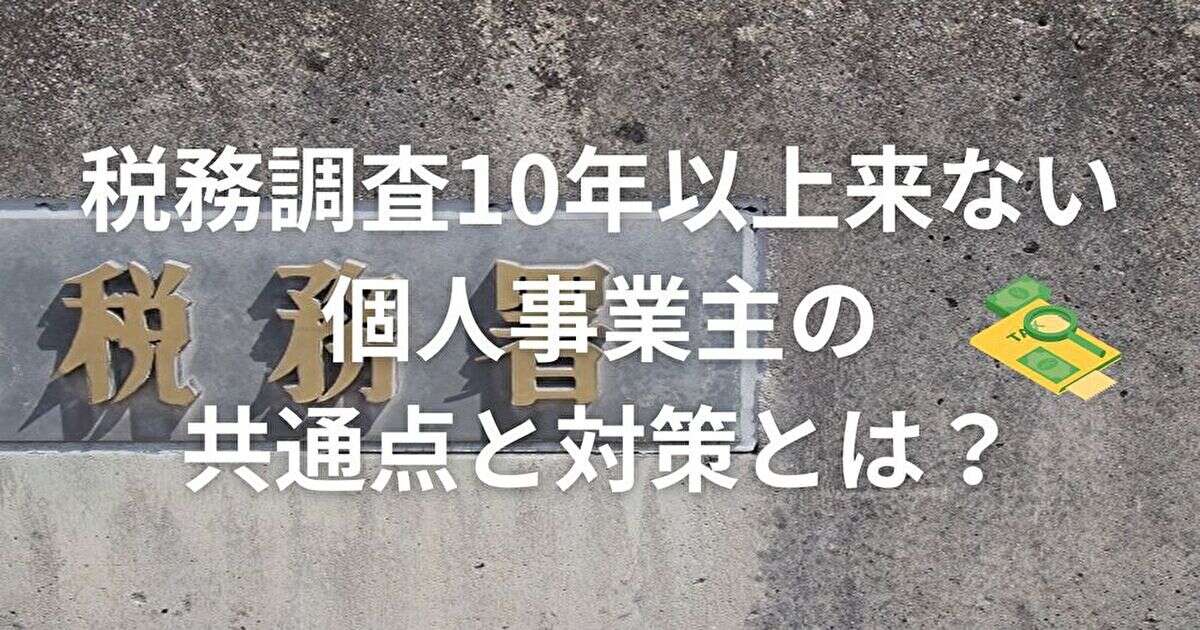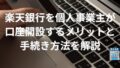記事のポイント
- 税務調査が10年以上来ない個人事業主の特徴や共通点を理解できる
- 税務調査が来る時期や対象となる基準を知ることができる
- 税務調査が来ない理由とその背景を把握できる
- 個人事業主が税務調査を避けるための対策を学べる
税務調査 10年以上来ない 個人事業主の特徴とは?

- 個人事業主が税務調査される確率は?
- 税務署に目をつけられる個人事業主は?
- 個人事業主の税務調査は何年後にされる?
- 税務調査 個人事業主はいくらから?
- 税務調査が来る時期の目安とは?
個人事業主が税務調査される確率は?
個人事業主が税務調査を受ける確率は、法人と比べると低い傾向にあります。しかし、まったくゼロではなく、業種や売上規模、申告内容によっては調査の対象になる可能性があります。
一般的に、税務調査の対象となるのは、所得が高い事業主や申告内容に不審な点がある場合です。国税庁が公表しているデータによると、個人事業主の税務調査率は法人よりも低いものの、業種によっては調査率が上昇することがあります。特に、現金取引が多い業種や、売上の規模が急激に伸びた事業者は、注意が必要です。
また、税務調査の確率を高める要因として、経費計上の不備や売上の申告漏れが挙げられます。例えば、実際には存在しない経費を計上していたり、大幅な赤字申告が続いていたりすると、税務署のチェックが入りやすくなります。このため、日頃から正確な記帳を行い、適正な申告を心がけることが重要です。
一方で、税務調査の確率を下げるためには、定期的に税理士と相談し、適正な会計処理を行うことが有効です。税務署は税理士が関与している事業者に対しては、申告内容が適正である可能性が高いと判断し、調査の優先度を下げることがあるためです。また、電子申告を利用することで、税務署からの信頼度を高めることができるとも言われています。

ちなみに下記の表は『事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位 10業種』になります。

国税庁(令和4事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について)
税務署に目をつけられる個人事業主は?
税務署が特に注目する個人事業主には、いくつかの特徴があります。単に売上が高いから調査されるわけではなく、申告内容や取引の透明性などが影響します。
まず、最も目をつけられやすいのは、売上の申告漏れが疑われるケースです。特に、現金取引が多い飲食業や美容業、建設業などでは、売上の一部を計上しない「売上除外」が発生しやすいとされ、税務署のチェックが厳しくなります。
また、クレジットカードや電子決済の導入が進んでいない事業者も、現金管理の透明性が低いため、調査対象になりやすい傾向があります。
次に、経費の計上が不自然な事業者も注意が必要です。たとえば、事業に関係のない支出を経費として計上していたり、家事関連費(個人的な支出と事業経費が混在している費用)を過大に計上していたりする場合、税務署から指摘を受ける可能性が高まります。特に、交際費や旅費交通費の金額が極端に多い場合は、不正計上を疑われやすいでしょう。
また、毎年の申告内容が大きく変動する事業者も、税務署の目に留まりやすくなります。たとえば、前年は大幅な利益を出していたのに、翌年突然赤字になった場合や、前年までの売上規模と比べて急に伸びた場合などは、不自然な会計処理が行われていないか確認される可能性があります。
さらに、過去に税務調査を受けた際に問題が指摘された事業者は、再調査の対象になりやすいと言われています。一度修正申告を求められた場合、税務署はその後の申告内容を注意深く監視しているため、同じような問題が続くと、再び調査が入る可能性が高くなります。
このように、税務署に目をつけられる事業者には共通した特徴があります。日頃から適正な帳簿管理を行い、申告内容に不自然な点がないようにすることが、税務調査を避けるための基本となります。
個人事業主の税務調査は何年後にされる?
税務調査が行われるタイミングは、事業主によって異なりますが、一般的に申告から数年後に実施されることが多いです。税務署が税務調査を行う際の基本的なルールとして、調査可能な期間(税務調査の時効)は最大7年間とされています。ただし、通常の税務調査は5年以内に実施されることが多いです。
特に、売上の規模が大きい個人事業主や、申告内容に不自然な点がある場合は、3年から5年程度で調査が入るケースが目立ちます。一方で、売上が少なく、特に問題がないと判断された事業者については、10年以上税務調査が来ないこともあります。

私は2014年にハウスクリーニング業で起業しましたが、今まで一度も税務調査は来たことがないです
また、税務署が税務調査を実施する際の優先順位は、業種や申告内容によって変わります。例えば、現金取引が多く、売上のごまかしが発生しやすい業種は、調査の頻度が高くなる傾向があります。逆に、電子帳簿を活用して適正に申告を行っている事業者は、調査の対象になりにくいこともあります。
さらに、税務署が調査に入るタイミングは、税務申告の内容だけでなく、他の事業者との取引関係にも影響されます。例えば、取引先の法人や個人事業主が税務調査を受け、その取引内容を詳しく調査する過程で、自社の申告内容にも疑問が生じた場合、連鎖的に調査が行われることがあります。
こうしたことから、個人事業主が税務調査を受けるタイミングは、一概に何年後とは言えません。しかし、税務署は基本的に数年ごとにリスクの高い事業者を選定し、調査を行うため、常に適正な申告を心がけることが大切です
税務調査 個人事業主はいくらから?
個人事業主が税務調査を受ける金額の明確な基準はありません。しかし、一般的に売上規模が大きくなるほど調査対象になりやすいと考えられています。特に、年間の売上が数千万円以上に達すると、税務署の監視対象となる可能性が高くなります。
税務署が税務調査の対象を決める際に注目するポイントは、単なる売上の金額だけではありません。不自然な経費計上や極端な利益率の変動なども、調査の対象となる要因となります。例えば、売上が1,000万円を超えているにもかかわらず、ほとんど利益を出していない場合、税務署は「経費を過剰に計上しているのではないか?」と疑うことがあります。
また、消費税の課税事業者になったタイミングも、税務調査が入るきっかけになることがあります。個人事業主は、売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となり、消費税の納付が義務付けられます。この際、消費税の申告や納付状況が適切でない場合、税務署の関心を引く可能性があります。
さらに、税務署が特に注目するのは「現金取引が多い事業者」です。たとえ売上が数百万円規模でも、現金取引が中心の業種(飲食店、美容室、建設業など)の場合、売上のごまかしが疑われやすくなります。そのため、たとえ大きな売上がなくても、帳簿の内容に不審な点があれば税務調査の対象となることがあります。
このように、「税務調査は〇〇円以上の売上がある場合に実施される」といった明確な基準は存在しません。しかし、売上が増えるほど調査対象になる可能性が高まること、そして経費計上の内容や取引の透明性も重要な判断基準となることを理解しておく必要があります。
税務調査が来る時期の目安とは?
税務調査が行われる時期には一定の傾向があります。特に、税務調査が集中しやすいのは「申告期限が終わった後の夏から秋」にかけてです。これは、税務署が確定申告のデータを分析し、不審な点がある事業者を選定する期間が春頃に集中するためです。
一般的に、税務調査の対象となる個人事業主には、過去の申告内容に不明瞭な点がある場合が多いです。特に、売上の申告漏れや経費の過大計上など、税務署が「修正が必要」と判断した場合に調査が行われます。そのため、前年の確定申告で不自然な点があると、翌年の夏から秋にかけて調査が入ることがあります。
また、業種によっても調査のタイミングが異なることがあります。例えば、飲食業や建設業など現金取引が多い業種は、確定申告の内容にかかわらず、数年ごとに調査が入ることがあります。一方、IT関連やコンサルタント業のように、取引がデジタル化されている業種は、税務署のチェックが入りにくい傾向にあります。
さらに、税務調査は「申告から3年〜5年の間に行われることが多い」と言われています。これは、税務調査の実施可能期間(時効)が通常5年であり、悪質な脱税の場合は7年まで遡れるためです。特に、過去に税務調査を受けたことがある事業者は、前回の調査から5年以内に再び調査が入ることがあるため、注意が必要です。
このように、税務調査が行われる時期には一定の目安があります。申告期限後の夏から秋にかけての時期が特に注意すべきタイミングであり、過去の申告内容によっては数年後に調査が入る可能性があることを理解しておくことが大切です。
税務調査 10年以上来ない 個人事業主が注意すべきこと

- 税務調査が来ない理由とは?
- 税務調査が全然来ない個人の共通点
- 税務調査は何年まで遡る?
- 税務調査が入ったら何をすべき
- 個人事業主が税務調査を避ける方法とは
- 税務調査が10年以上来ない個人事業主の特徴とは
税務調査が来ない理由とは?
個人事業主の中には、10年以上税務調査を受けたことがない人もいます。税務調査が来ない理由はいくつか考えられますが、主に
- 申告が適正である
- 調査の優先度が低い
- 税務署に特に目をつけられていない
といった要因が挙げられます。
まず、申告が適正である場合、税務調査の必要性が低くなります。例えば、売上や経費の申告が毎年安定しており、不自然な変動がない場合、税務署は「適正な申告が行われている」と判断しやすくなります。また、税理士が関与している事業者は、申告の信頼性が高いとみなされるため、調査の対象になりにくい傾向があります。
次に、税務調査の優先度の問題も関係しています。税務署の調査リソースには限りがあり、全ての個人事業主を一斉に調査することはできません。そのため、税務署は「税額の影響が大きい事業者」や「申告内容に不審点がある事業者」を優先的に調査します。逆に、売上規模が小さく、特に問題がない事業者は、調査の優先度が下がるため、結果的に長期間税務調査が来ないことがあります。
さらに、税務署に目をつけられていない事業者も、税務調査が来にくい傾向があります。例えば、現金取引の割合が低く、取引内容が明確である業種(IT業、デザイン業、コンサル業など)は、税務署のチェック対象になりにくいとされています。また、毎年の申告が電子申告で行われ、取引記録が整っている場合も、税務調査のリスクが低くなります。
ただし、「税務調査が来ない=問題がない」とは限りません。たとえ10年以上税務調査が来ていなくても、突然調査が入ることは十分あり得ます。また、仮に誤った申告を続けていた場合、過去に遡って修正を求められる可能性もあるため、税務調査が来ないことを理由に油断するのは危険です。
このように、税務調査が来ない理由はいくつかありますが、だからといって油断せず、常に正しい申告を心がけることが大切です。
税務調査が全然来ない個人の共通点
税務調査が全く来ない個人事業主には、いくつかの共通点があります。これらの要因を理解することで、自身の状況と照らし合わせ、適正な申告を続けるための参考にすることができます。
まず、税務調査が来ない個人の大きな特徴として「申告が正確であること」が挙げられます。税務署は、基本的に「申告内容に不審な点がある事業者」を優先的に調査します。そのため、毎年の確定申告で売上・経費のバランスが適正であり、不自然な増減がない場合、調査の必要性が低いと判断される可能性が高くなります。
また、「売上規模が小さい」ことも、税務調査が来ない理由の一つです。税務署は限られた人員の中で、効率的に税収を確保する必要があります。そのため、売上が数百万円程度の小規模な事業者よりも、数千万円以上の規模の事業者を優先的に調査する傾向があります。
さらに、「税理士が関与している」場合も税務調査のリスクが低くなる傾向があります。税理士が適切に申告をサポートしていると、税務署は「申告内容の信頼性が高い」と判断しやすくなります。特に、税理士が作成した決算書や申告書には「税理士の署名」が入るため、不正リスクが低いと見なされやすいのです。
また、「現金取引が少ない業種」も税務調査が入りにくい特徴の一つです。例えば、IT業やコンサル業のように、銀行振込が主体の事業では、売上のごまかしがしにくいため、税務署の調査対象になりにくい傾向があります。一方、飲食業や小売業のように現金取引が多い事業は、売上の申告漏れが疑われやすく、調査が入りやすくなります。
ただし、「税務調査が来ない=安心」とは言い切れません。長年調査が入らなくても、ある日突然税務署から連絡が入る可能性はあります。過去の申告に問題がある場合、数年分まとめて指摘されることもあるため、常に正しい申告を心がけることが重要です。
税務調査が全然来ない個人の共通点
- 申告が正確であること
- 売上規模が小さい
- 税理士が関与している
- 現金取引が少ない業種

税理士については下記の記事を参考にしてくださいね
税理士紹介エージェントで最適な税理士を見つける方法
税務調査は何年まで遡る?
税務調査では、過去の申告内容を遡って調査されることがあります。一般的には「5年」が基本とされていますが、悪質な場合は「7年」まで遡られることがあります。
通常、税務署が税務調査を実施する際は、過去3年〜5年分の確定申告を対象にすることが多いです。これは、税務調査の時効が原則5年であるためです。例えば、2025年に税務調査が入った場合、2020年から2024年までの申告内容がチェックされることになります。
ただし、悪質な申告漏れや意図的な脱税が発覚した場合、調査期間は最大7年まで延長されることがあります。これは、税法上の「重加算税」の適用対象となるケースであり、例えば売上を意図的に隠していたり、架空の経費を計上していた場合などが該当します。この場合、税務署は2018年まで遡って調査を行うことが可能です。
また、税務調査の対象となる年数は、事業の状況によっても変わります。例えば、新規開業したばかりの事業者の場合、開業から3年間は調査が入りにくいことが多いですが、その後の申告内容によっては4年目以降にまとめて調査が入ることがあります。
一方で、申告内容に問題がなく、税務署から特に指摘を受けていない場合は、5年以上経過した分については調査が行われないことが一般的です。そのため、過去の申告に誤りがあった場合は、早めに自主的に修正申告を行うことがリスク回避につながります。
このように、税務調査は通常5年、悪質な場合は7年まで遡って行われます。適切な申告を続けることで、万が一の調査にも冷静に対応できるようにしておくことが重要です。
税務調査が入ったら何をすべき
税務調査の通知を受けた際、適切に対応することで調査の負担を軽減し、不要な指摘を受けるリスクを下げることができます。税務調査の流れを把握し、事前に準備を進めることが重要です。
まず、税務調査の通知が来たら、調査の日程や範囲を確認しましょう。通常、税務署から事前に電話や書面で通知があり、調査対象となる年度や、必要な資料が伝えられます。慌てずに内容を整理し、対応する準備を進めることが大切です。もし不明点がある場合は、税務署に問い合わせるか、税理士に相談するとよいでしょう。
次に、必要な書類を整えます。税務調査では、確定申告書や帳簿、領収書、請求書、通帳のコピーなどの提出が求められることが一般的です。これらの書類が不足していると、税務署から指摘を受けやすくなるため、事前に漏れがないか確認しておきましょう。また、申告内容と実際の取引が一致しているかもチェックし、万が一誤りがあれば、事前に修正を検討することが重要です。
税務調査当日は、誠実な態度で対応することが求められます。調査官の質問には正直に答え、曖昧な回答は避けることが大切です。不明な点があれば、後日書類を提出する旨を伝え、安易に適当な返答をしないようにしましょう。また、調査官は納税者の態度や言動を注意深く見ているため、不必要に警戒したり、敵対的な態度を取るのは避けるべきです。
税務調査の結果、指摘を受けた場合は、冷静に対応しましょう。過少申告や経費の計上ミスがあった場合は、修正申告を行い、必要な税金を納めることで問題を解決できます。悪質な脱税と判断されない限り、適切に対応すれば過度なペナルティを受けることはありません。
税務調査は、事業の透明性を保つための重要な手続きです。適切な準備と対応を心がけることで、調査の負担を最小限に抑え、スムーズに進めることができます。
個人事業主が税務調査を避ける方法とは
個人事業主が税務調査を避けるためには、日頃から適正な申告と管理を徹底することが不可欠です。税務署が調査を行う主な理由は「申告内容に疑問がある場合」や「不正の可能性が高い場合」です。そのため、税務署に不信感を抱かれないような対策を取ることが、税務調査を避けるポイントとなります。
まず、正確な帳簿をつけることが最も重要です。売上や経費の記録を曖昧にせず、日々の取引を適切に記帳しましょう。特に、経費の計上については、領収書や請求書をしっかり保管し、必要に応じて説明できる状態にしておくことが大切です。電子帳簿保存を活用することで、管理の手間を減らし、税務署からの信用度を高めることができます。
また、売上や経費の増減が極端にならないよう注意しましょう。例えば、前年と比べて売上が大幅に減少していたり、不自然な経費が増えていると、税務署の目に留まりやすくなります。特に、接待交際費や広告宣伝費などの経費が多すぎる場合、税務調査の対象になる可能性が高まるため、合理的な範囲で計上することが求められます。
税理士を活用することも、税務調査を回避する方法の一つです。税理士が関与している場合、税務署は「申告内容の信頼性が高い」と判断することが多く、調査対象になりにくい傾向があります。特に、税理士が作成した申告書には「税理士の署名」が入るため、不正リスクが低いと見なされやすいのです。
さらに、税務署からの問い合わせには迅速かつ誠実に対応することも重要です。税務署から「お尋ね文書」などの問い合わせが届いた際、無視したり、適当に返答すると、税務署は「何か問題があるのではないか」と判断し、調査につながる可能性があります。適切な対応をすることで、税務署からの疑念を払拭し、税務調査のリスクを軽減できます。
最後に、過去の申告内容を定期的に見直し、誤りがあれば自主的に修正申告を行うことも効果的です。税務署は「自主的に修正する事業者」に対しては寛容な対応をすることが多く、税務調査の優先度が低くなる可能性があります。
税務調査を完全に避けることは難しいですが、適正な申告と適切な対応を続けることで、調査のリスクを最小限に抑えることができます。日頃からの正確な管理と慎重な対応が、税務調査を避けるための最も確実な方法と言えるでしょう。